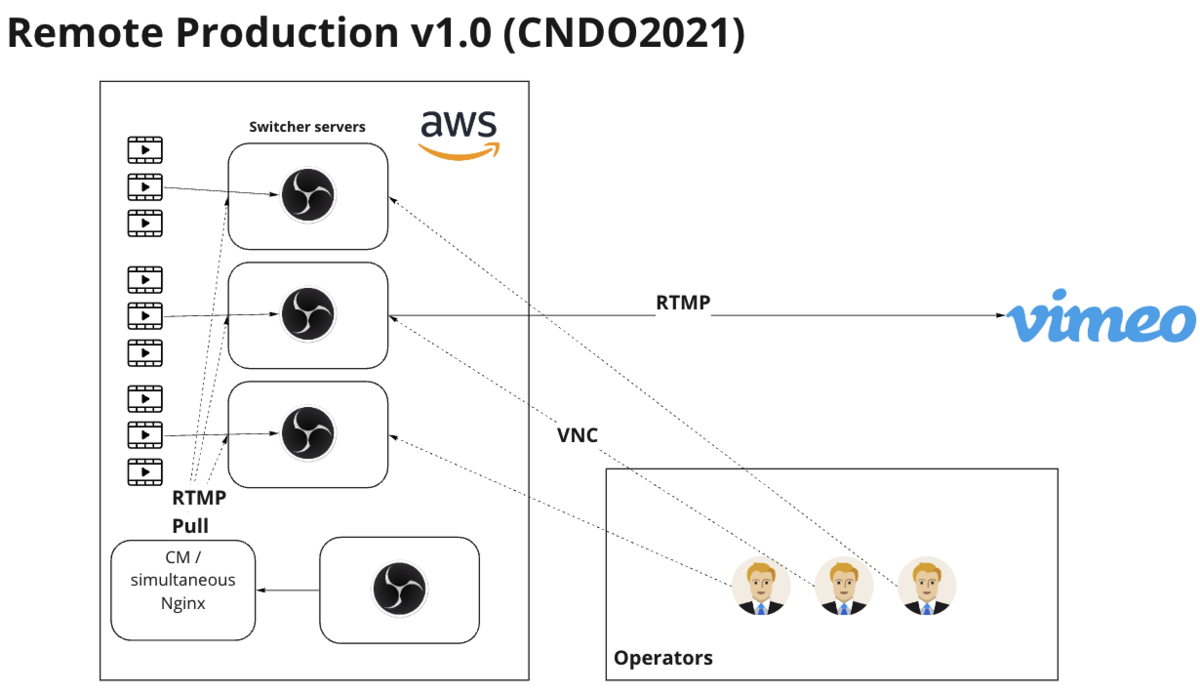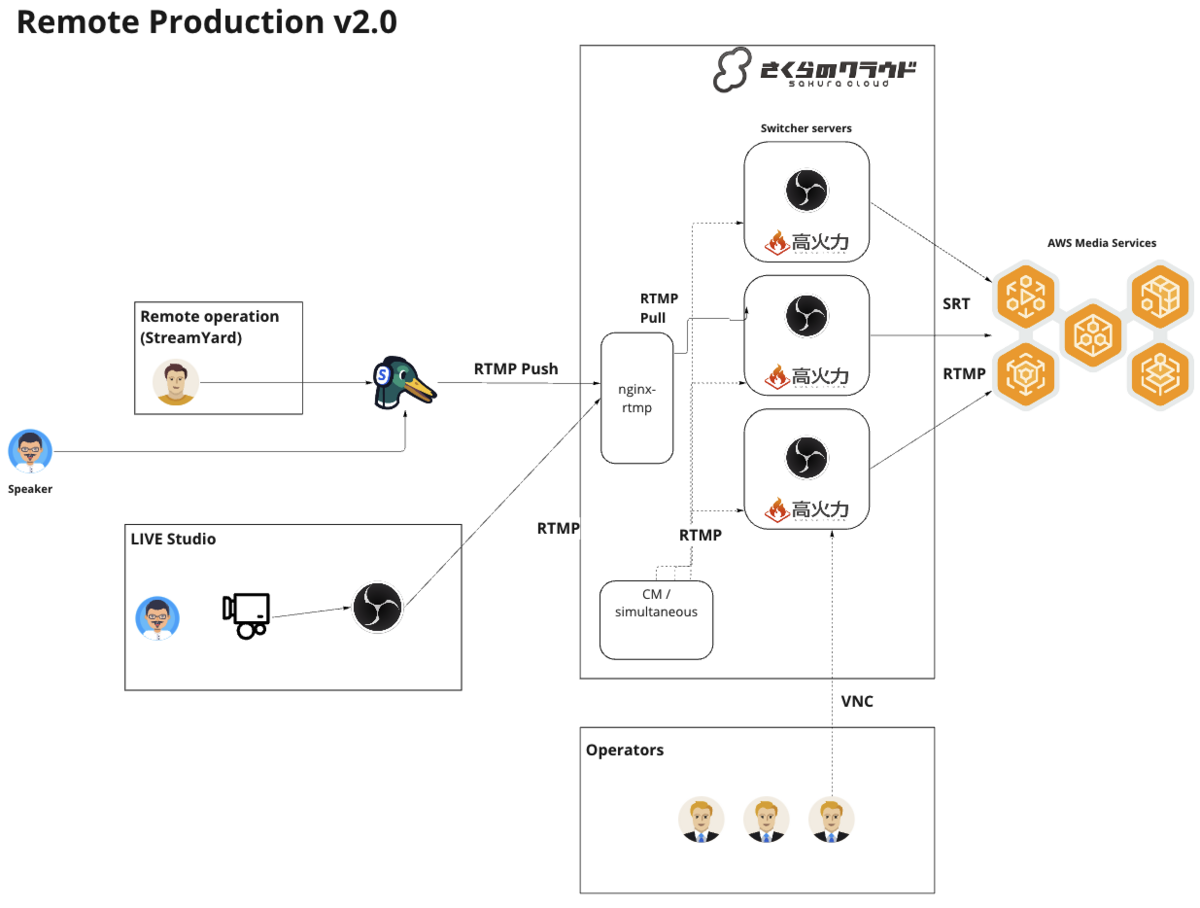こういう記事があった。
自分は2019年から2023年までCloudNative Daysという国内最大のクラウドネイティブ技術カンファレンスのCo-chairを務めていたり、今年はPlatform Engineering Kaigi 2024というカンファレンスの代表をしている。最近ではカンファレンスやミートアップをやっていくための一般社団法人クラウドネイティブイノベーターズ協会を立ち上げたり、タダ飯おじさんと対決したりと、コミュニティ作りに対しては思い入れが強いほうだと自負している。
そんななかで目にしたのが冒頭の記事だ。 記事の大意としては「カンファレンスに参加するのであれば、目的意識を持った方が得られるものが多い」という話であり、それ自体は特に否定するものではない。ただし、その説明に使われている理由や、タイトルに使われている「なんとなく」や「ただ楽しいから」というモチベーションに対する疑義というのが、少なくとも主催者側の想いとは異なっているのではないかなと感じた。
結論から言うと、カンファレンスに参加する目的は「なんとなく」や「ただ楽しいから」で良いし、一分一秒を無駄にしないという考え方も不要。気軽に参加するべきだ。
全ては「なんとなく」から始まる
自分が初めて技術カンファレンスに参加したのは15年くらい前。RubyKaigi2009だったと思うが、当時まだ駆け出しのエンジニアだった自分は、話されている内容の2割か3割程度しか理解出来なかったと思う。それでも、日本中からたくさんのエンジニアが集まって一つの技術カテゴリについて熱く語っている様子に圧倒された記憶がある。
はじめてカンファレンスに参加する人の多くは「なんとなく興味があるから」で参加し、そして圧倒されて帰っていく。でも、それがいいのだ。
はじめからしっかりとした目的意識を持てる人なんてほとんど居ない。目的意識というものは、あらかじめ対象カテゴリに対して体系的に理解出来る素地があり、それを自分事に変換して捉えられるだけの経験があってはじめて生まれるものだ。 そもそも技術カンファレンスは、その体系的な知識や他者の生きた経験を学べる場なのだから、参加する前は目的意識がなくて当然なのだ。
まずは「なんとなく」で全然OK。気軽に飛び込んできて欲しい。むしろカンファレンス主催者としてはそういう人こそウェルカム。
そして雰囲気に圧倒されるといい。そうすると「なんとなく」自分の課題感や短期的に目指すべきところが見えてくる。とはいえ1回や2回参加しただけではまだ輪郭がぼやけているかもしれないが、気にしなくて良い。それはそういうものだ。なんとなくの参加を繰り返していくと、だんだんハッキリとしてくる。
元記事でも紹介されているこちらの記事が興味深いが、個人的にはこの自分事に変換して捉える能力というのは、意識よりもシンプルに「場数」だと考えている。より効率を上げるための「工夫」はあるが、何よりもまずは場数が大事。
場数を増やすにもっとも効くモチベーションは「楽しいから」という感覚だ。カンファレンスに参加して「楽しい」と思える能力は、ただそれだけで価値がある。楽しいと感じたのであれば、あとは細かなことは気にせず、その感覚を忘れずに繰り返していくことをお勧めしたい。
コスパ、タイパでは測りづらい「社会資本」という考え方
カンファレンスに参加することで得られるものは技術知識だけではない。人とのネットワークといった「社会資本」も、得られるものとして重要だ。
ネットワークとか社会資本って言うとお堅い感じがして嫌だなと思うのであれば、「気が合う仲間づくり」くらいに考えて差し支えない。そこで得られた仲間は、数年、数十年、もしかすると一生において大切なものになるかもしれない。
じゃあこういった仲間が1回カンファレンスに参加するだけで出来るかというと、それは難しい。世の中には一発で友達作れちゃうコミュ強も存在するが、多くの人はそうじゃない。2回参加すると「あの人前も居た気がするな」となり、3,4回目になると「ちょっと声かけてみようかな」となってはじめてコミュニケーションが取れるようになる。
なので、カンファレンス主催者はそのあたりも考慮して場を設計する。まずはソロでも楽しめるコンテンツ作りをして、次も来て貰えるようにする。次に、ネットワーキングのための懇親会を用意して話せるようにしたり、ランダムにグループを組ませて交流を作るワークショップを用意したりと、あらゆる工夫をこなすのだ。
そのためには、とにかくハードルを下げまくって、いろんな人に来て欲しいと思っている。「なんとなく」の参加大歓迎。「ただ楽しいから」のリピーター大歓迎。そういった人たちを繋げて、モチベートして、お互いに成長してもらう。それが主催としての醍醐味だ。
そもそも、こういうコミュニケーションをコスパやタイパで測ることは難しい。信頼関係の醸成というのは、単に時間やお金だけの問題ではないからだ。
ビジネスの場における信頼関係の醸成のために、よくゴルフや会食などが用いられる。日本に限らず世界中で活用されている手法で非常に効果があるものだが、じゃあそこにゴルフ1ラウンドあたりのコストパフォーマンスが・・・なんて考える人はいない。そうではなく、普段の活動含めて全体的な取り組みとして信頼関係を築いて、最終的にはお互いにプラスになっていくのである。
なので、カンファレンスに参加するのに1分1秒も無駄にしないといった考え方は、ややToo Muchなのではないか。カンファレンス参加や普段の情報発信を含めて、トータルでプラスになっていればそれでいいという、軽い考えのほうがよい。
友達づきあいでも、SNSでも、合コンでもそうだが、人が関わる場でコスパ・タイパを重視しすぎるのは疲れのもと。ガツガツいくと、かえって上手くいかないものだ。
上でも述べたように、人付き合いでも知識の吸収でも、大事なのは「場数」。そのためには、疲れを減らして長く継続するサステナビリティが重要だ。そういう観点でも、「なんとなく」「楽しいから」程度のゆるい参加で良いと思うのだ。
そもそも主催はコスパ・タイパ最悪。だが、それがいい
実はこの記事は、大阪に向かう新幹線の中で書いている。Platform Engineering Meetupを大阪で開催するために、30kg近い配信機材を転がしながら新幹線乗り込んだのだ。
platformengineering.connpass.com
なんとか仕事に都合をつけて、数時間という移動時間を費やして、無料のミートアップの開催のために遠征をしている。コスパ・タイパでいうと最悪だ。というかマイナスだし。
じゃあ何故そこまでして主催をするのか。もちろんPlatform Engineeringという考え方を広めていきたいという想いはある。でも、それだけではない、マグマのようなこの突き動かされるようなモチベーションはどこから来ているかというと、これまた「なんとなく」であり「楽しいから」だ。
正直なんで地方でやるの?と言われたとき、合理的な説明はできない。「でもなんか、知らない土地でやるのも楽しいじゃん?」「たこ焼き、お好み焼き食べたいじゃん?」本気でこんなもんである。
東京でのカンファレンス開催も一緒。ものすごく多くの時間を費やしているし、地味な事務作業だってやらないといけないし、イベントに関係ないモメ事にも対処しないといけない。実行委員同士の関係性が悪くなったりだとか、ごく稀ではあるが痴情のもつれが起きたりもする。だって人間だもの、仕方が無い。でも、そういうのにもちゃんと対処しないと、良いイベントはできない。
このコスパ・タイパ最悪な取り組みを、何年にもわたって続けられるモチベーション。それは全て「なんとなく」であり「楽しいから」。
ただまあ、この十数年を振り返って、トータルで見たときに自分が損をしているかというと全くそうは思わない。大きなイベントをやってきた経験、人を楽しませる企画をした経験、人を率いた経験、人から向けられる評価というのは、今の自分において圧倒的な強みとなっているし、心のそこからやって良かったと思っている。
個々の取り組みのコスパを考え始めると、おそらくこれは続られなかっただろうと思う。また、偉大な先人たちが開催してくれたイベントに参加できたからこそ、ここに至れたのだ。
こういった経験があるからこそ、イベントに参加する人には「なんとなく」であり「楽しいから」だけでいいから来て欲しいなって思う。
ということで、ちょうど大阪についたので今回はこの辺で。
追記
あ、ひとつ大事なことを忘れていた。
軽い感じでカンファレンスに来てほしいけど、セッション中に寝たりとかスマホゲーするのは駄目です。それは単純に登壇者に対する無礼なので。
眠たければどこか他の場所で仮眠するか、家に帰って寝よう。
ゲームは家でやろう。